オペラ全曲ざっくり解説の文字起こしです。
聴きながら読むと分かりやすい! 音声はこちら↓
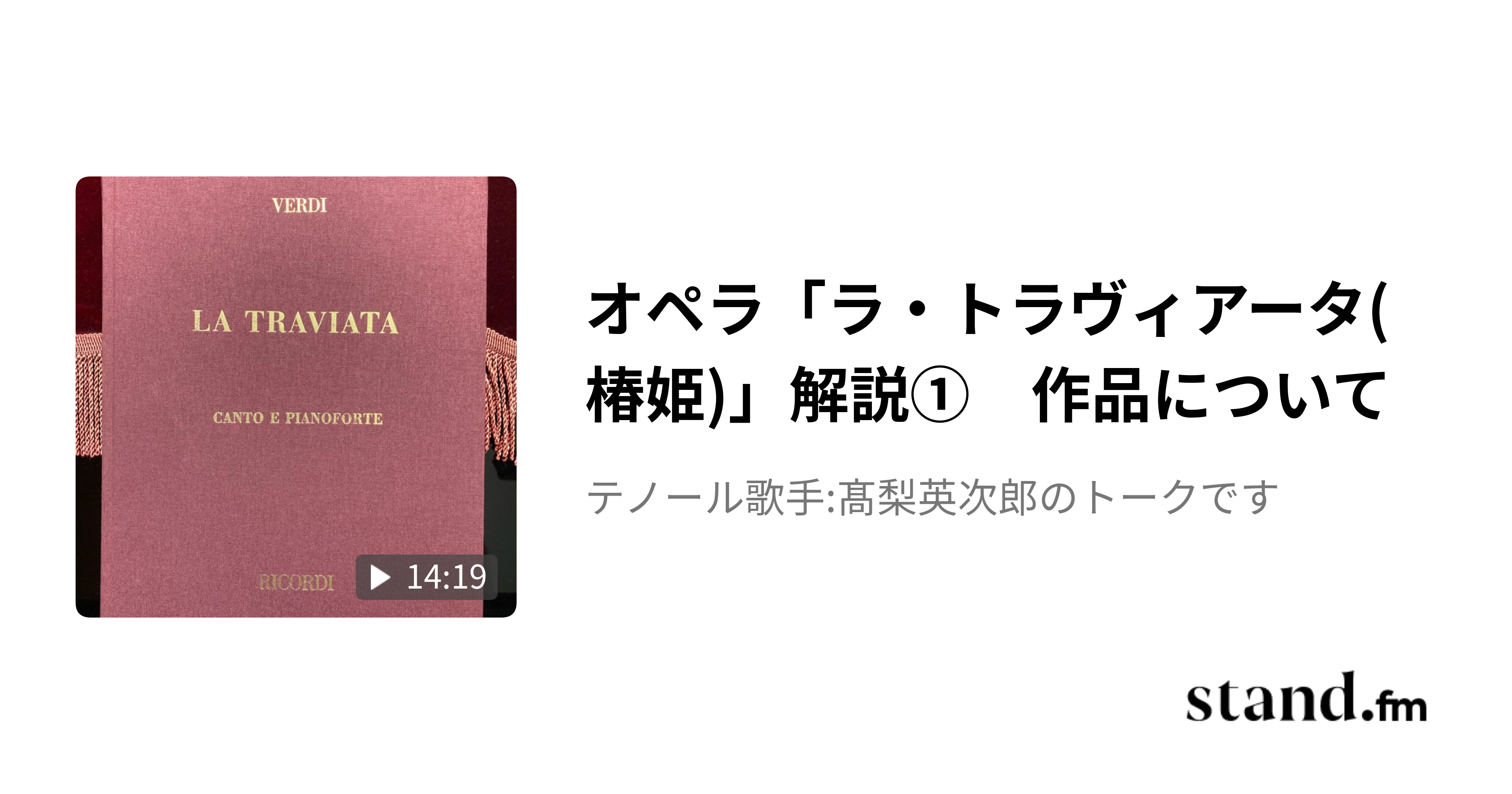
こんにちは!テノール歌手の髙梨英次郎です。
本日もオペラをざっくり解説して参ります。
オペラって面白いですよ!
今回は、ヴェルディ作曲19作目のオペラ「ラ・トラヴィアータ」、またの名を「椿姫」です。
トラヴィアータとは日本語で、「道を外れた女」という意味です。
「椿姫」は、オペラの原作となった小説及び舞台戯曲の「椿を持った婦人 La Dame aux camélias」から、訳された題名ですが、オペラの正式題名は「ラ・トラヴィアータ」です。
ここでは、原作とオペラの違いが分かるよう、オペラは「ラ・トラヴィアータ」と呼んでご紹介いたします。
このオペラは、ヴェルディの全作品の中でも1,2を争うほど有名な作品で、ヴェルディの代表作とも見られがちなのですが、これまでのヴェルディの作品、そしてこれからの作品においても、どれ一つ似たものはありません。
よって、代表作というよりはむしろ、異色作と言えます。
現代に至るまで本当に多く上演されているこの「ラ・トラヴィアータ」、こちらと、「カルメン」「蝶々夫人」を並べて、”世界3大プリマ・ドンナ・オペラ”と紹介する書籍もあり、私もそれに同意します。
この3作品に共通するのは、オペラの全幕を通して、主役として1人の女性に徹底的にスポットが当たっており、彼女の心情、事件、人生が歌と音楽によって徹頭徹尾表現されている、ということが挙げられます。
その先駆けとなったのがこの「ラ・トラヴィアータ」です。
この作品の主人公は、”高級娼婦”とされる地位、職業についていた女性です。
オペラの主人公ヴィオレッタ・ヴァレリーの元となったのは、原作のマルグリット・ゴーティエ。
そしてマルグリットの元となったのが、実在したマリー・デュプレシという女性です。

Marie Duplessis
マリーは、貧しい家庭に生まれ、どうしようもないロクデナシの父親のもと、その少女時代はとても苦しい体験もしてきたのですが、生来の美貌と才能で、パリ裏社交界の花形となっていきました。
裕福な、主に貴族の男性に見初められることによって、いわばその愛人のようになっていくのですが、そういった貴族に見初められるためには、エレガントな立ち居振る舞いや知性が必要で、マリーは最初は苦労したようですが、急速にそういった要素を身につけて、幾人もの男性貴族の間を渡り歩いていったのでした。
「ダルタニアン物語(三銃士)」や「モンテ・クリスト伯」などの作品で有名な作家アレクサンドル・デュマには、同じアレクサンドルという名前の息子がいました。
区別するために、デュマ・ペール(父)とデュマ・フィス(息子)と呼び分けることがあります。
デュマ・フィス(息子)は、20歳の頃に、同い年のマリー・デュプレシと知り合い、恋に落ちます。
マリーは常に椿の花を身に着けていましたが、月のうち白い椿をつけている時はデート可能、月に5,6日赤い椿をつけている時はダメ。
この理由は、ストレートに口にするのは憚られますが、女性の月の事情に即したものである、ということです。
デュマ・フィスはまだ駆け出しにもなっていない状態で、父親に金を無心してマリーとデートするという、どら息子状態でしたが、マリーとしては、金のある貴族にはない純粋さをデュマ・フィスに感じたのでしょうか、その恋愛は数か月続きました。

Alexandre Dumas fils
が、その後も高級娼婦としての務めはやめないマリーに対して、次第にデュマ・フィスの方が嫉妬に耐えられなくなり、ついには別れの手紙をマリーに書き残して、2人は別れてしまいます。
その後もマリーはフランツ・リストと恋仲になったり、ある伯爵と婚姻関係を結んだりもしますが、持病の肺結核が悪化して、1847年2月、23歳でその生涯を閉じます。
マリーの死後、デュマ・フィスは、おそらく自らの体験をもとにしたであろう小説「椿姫」を発表します。
小説では、アルマン・デュヴァルという青年が、マルグリット・ゴーティエという女性に恋をします。
マルグリットもマリー・デュプレシと同様、パリの裏社交界を儚くも華麗に生きる高級娼婦として描かれています。
しかし、アルマンとマルグリットが別れてしまう原因が、事実とは決定的に違いました。
息子が高級娼婦と同棲していると聞きつけたアルマンの父親が、マルグリットに息子と別れるよう告げに来ます。
アルマンを心から愛していたマルグリットは、アルマンの将来の為にと、泣く泣く別れる決意をして、アルマンの元から去ります。
アルマンは父親の行動を知らず、マルグリットに裏切られたと思い、外国へ旅立ちます。
やがてマルグリットが病気で危篤になったと知ったアルマンは急いでパリに戻りますが、時すでに遅く、マルグリットは亡くなっていて、彼女が残した手記を読んで、マルグリットは自分への愛を唯一の希望にしていた、ということをアルマンは知る…。
こういったお話になっています。
この原作は現在でも日本語で読めます。オペラでは描かれない、大変興味深くショッキングなシーンもあったりしますので、是非、お読みいただきたいと思います。
この作品がデュマ・フィス自身によって戯曲化されて、1850年に舞台で上演されると大ヒットとなりました。
それは、あのユーゴ―作「エルナニ」に次ぐ事件、とも呼べるほどのセンセーショナルな大ヒットだったそうです。
その後も現在まで、この舞台版も上演されていますし、映画化もされています。
個人的には、グレタ・ガルボがマルグリットを演じた映画版が特に好きです。
この舞台版をヴェルディもパリで鑑賞しました。
この頃ヴェルディは、恋人のジュゼッピーナ・ストレッポーニと共にパリに滞在していました。
他の作品の解説で、ジュゼッピーナがヴェルディの地元ブッセートの住民に受け入れられず、あからさまに無視されたり避けられたりしていたことをお話してきました。
ソプラノ歌手であったジュゼッピーナには、結婚していない状態で産んだ私生児がいたりして、当時のキリスト教道徳観念から言えば、ふしだらな女性と見られてしまっていたのです。
今よりも女性の働き口が限られていたこの時代、歌手やダンサーの社会的地位は低いものでした。
そんなジュゼッピーナの状況には本人はもちろん、ヴェルディも苦悩と怒り、悲しみを覚えていたと思われます。
パリから戻って、ヴェネツィアとの新作発表の契約のため、ヴェルディはこの「椿姫」をオペラ化することを決めます。
台本は、ヴェルディに忠実な”いい人”でおなじみの、ピア―ヴェ。
この作品をオペラ化するにあたって、ヴェルディとしてはジュゼッピーナの存在が念頭にあったことは、まず間違いないでしょう。
ただ、娼婦を題材にした戯曲、演劇がセンセーショナルな事件になったのと同様に、こういった題材をオペラ化することも当時としては全くの常識外れなことでした。
しかもこのお話は、初演当時が舞台の現代劇。
いわば、現代社会のタブーに切り込む、ということになり、タブーであるからには、政府当局からの検閲の対象になってしまいます。
ですがヴェルディとしては、社会批判をしたいわけではなく、1人の女性、人間の心情や葛藤を描きたいと思っているだけなので、例によってピア―ヴェは、そういったヴェルディの意図を一生懸命政府に主張して、説得を繰り返して、上演の許可を取ることが出来ました。
ただ、それでも多少の忖度をしたピア―ヴェと劇場側は、本番の衣装を150年も前の時代設定にして、現代劇とわからないように、ぼかすことにしました。
お話の内容からして、それだとちぐはぐに見えてしまうのですけれどね…。

さて初演のために歌手が集められたのですが、ヴェルディは主人公ヴィオレッタを演じるソプラノ歌手ドナテッリにたいそう不満を持っていました。

Fanny Salvini-Donatelli
歌唱力は申し分ないのですが、どうも体格がしっかりめの女性だったようで、とても肺病で亡くなるようには見えなかったそうなのです。
それでも契約とか色々な大人の事情で、交代はできぬまま、初演の幕が上がります。
1853年3月6日、ヴェネツィア、ラ・フェニーチェ劇場、ヴェルディ39歳。

Giuseppe Verdi
ヴェルディは知人への手紙に書いています。
「昨夜は大失敗でした。私のせいか歌手たちのせいか、時がたてばわかるでしょう」
とのことで、初演が失敗したのに後の世で名作となった、という例の一つとなってしまいます。
ですが、近年の研究では、ヴェルディが言うほどの失敗ではなかったのではないか、という見方がされています。
主演ソプラノのドナテッリには、少なくとも第1幕は喝采が起きたようですし、初演後も9回上演されています。
ヴェルディが危惧した通り、ヴィオレッタが肺病で弱っている第3幕では客席から失笑が漏れた、ということもあったようで、おそらくそういったことがヴェルディにとっては大変悔しく、その後、「トラヴィアータ」の総譜(フルスコア)を出版することを見送るよう、出版社リコルディに指示します。他の劇場からの再演依頼も断りました。
ヴェルディとしては、自分が納得できるキャストで、完全な形で上演したいと思っていたのです。
初演から1年後、1854年5月にヴェネツィアのサン・ベネデット劇場で行われた再演では、歌手を慎重に選んで、稽古も十分に重ねての本番を迎えられ、そちらは大変な成功を収めました。
そこで初めてヴェルディは総譜の出版を許可しました。
こうして「ラ・トラヴィアータ」は世界中で上演される大人気オペラとなっていったのでした。
名作中の名作で、やはりここまで長くなってしまいましたので、ストーリについては次回お送り致します。
お楽しみに!
ありがとうございました。
髙梨英次郎でした。
参考文献(敬称略)
小畑恒夫「ヴェルディ 人と作品シリーズ」
ジュゼッペ・タロッツィ「評伝 ヴェルディ」小畑恒夫・訳
永竹由幸「ヴェルディのオペラ」「オペラになった高級娼婦」
秦 早穂子「『椿姫』と娼婦マリ」
髙崎保男「ヴェルディ 全オペラ解説」


コメント